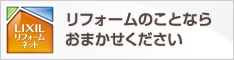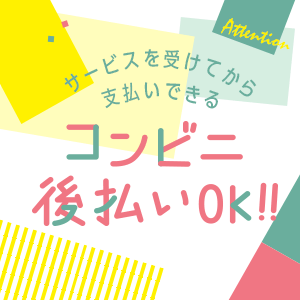水のコラム
止水栓の不調は要注意!自分で交換するときの流れと注意点【水道職人:公式】

水まわり設備の不具合やメンテナンス時に重要な役割を果たす「止水栓」。
水漏れの修理や水まわり設備の交換時にはこの止水栓を操作して給水を止める必要がありますが、経年劣化によってハンドルが回らなくなっていることがあります。
いざというときにきちんと機能しない止水栓は、暮らしの安全を脅かす要因になりかねません。
今回は、止水栓を交換すべきタイミングや、その手順についてご紹介します。
水まわり設備の安全管理の一環として、止水栓の状態を把握しておくことは非常に重要となるため、参考にしてみてください。
止水栓の役割と重要性

止水栓とは、水まわり設備に設置されている、各設備の給水を制御する役割を持った「栓」です。
台所や洗面台、トイレ、洗濯機の壁・床などに設置されており、水まわりの修理や点検の際に対象設備の給水だけを止水できます。
万が一の水漏れや水まわり設備の交換時に、水道の元栓を閉めることなく局所的に水を止められるため、非常に便利で重要な栓と言えるでしょう。
また、賃貸住宅などでは止水栓を閉めることで、退去時の水道工事をスムーズに行えるという面もあります。
ただし、止水栓は蛇口などの水まわり設備と同様に、長年の使用により劣化したり、サビついたりすることがあります。
その結果、止水栓を回せなくなり、給水を止められなくなることがあるのです。
止水栓を常に使用可能な状態に保つためには、定期的な点検と、必要に応じた交換が欠かせません。
止水栓の交換が必要なタイミング

止水栓を交換すべきタイミングには、いくつかの具体的なサインがあります。
次のような症状が見られる場合は、早めの交換をご検討ください。
1つ目は、「止水しても水が止まらない」場合です。
これは内部パッキンの劣化や、ハンドルの摩耗によって水が漏れてくる典型的な症状だと言えるでしょう。
2つ目は、「止水栓が固着して回らない」場合です。
サビや汚れがたまっていると、ハンドルが固着して動かず、緊急時に止水できなくなる恐れがあります。
3つ目は、「水が漏れている」ケースです。
止水栓そのものやその接続部分から水がにじみ出ている状態は、明らかな劣化のサインです。
4つ目は、「水まわり設備交換時の予防的な交換」です。
トイレ本体や洗面台の交換時などに、止水栓も同時に新しいものへ交換しておくと安心です。
また、止水栓の寿命は10年程度だと言われています。
そのため、設置から10年以上が経過している場合、目立った不具合がなくても劣化が進んでいる可能性があるのです。
とくに、築年数が経った住宅では、止水栓の部品そのものがすでに流通していないケースもあるため、早めの交換が推奨されます。
止水栓の主な種類とそれぞれの特徴

止水栓にはいくつか種類があり、交換の際には場所ごとに適したものを選定することが大切です。
キッチンや洗面台で一般的なのは「ハンドル式止水栓」です。
この止水栓は手で回すタイプのもので、道具不要で回せるため、緊急時でも回しやすいという特徴があります。
シンプルで扱いやすい反面、固着して手で回せなくなることがあります。
トイレや浴室で一般的なのは「ドライバー式止水栓」です。
この止水栓はマイナスドライバーなどで回して操作するタイプで、トイレや浴室など、大きめの止水栓では邪魔になる場所で使用されている傾向があります。
蛇口と間違って回してしまう誤操作が少ないという利点がありますが、マイナスドライバーなどの道具がないと回せないという不便さもあります。
止水栓の中には「ボール式止水栓」というレバー型のものもありますが、一般のご家庭では目にする機会は少ないかもしれません。
この止水栓は操作が簡単で、瞬時に水を止められるため、介護施設や公共施設などで使用されています。
交換の際は、既存の止水栓の形式に合わせて、同じ型を選ぶのが基本です。
止水栓の交換に必要な道具

止水栓の交換には、いくつかの道具が必要です。
交換作業を行う前に準備しておきましょう。
【止水栓の交換に必要な道具】
- モンキーレンチ(またはスパナやウォーターポンププライヤー)
- マイナスドライバー
- 止水栓本体
- シールテープ
- 雑巾やバケツ
また、作業中に水が出てくる可能性があるため、周辺の床・壁を保護する新聞紙や養生シートを敷いておくと安心です。
止水栓には設置場所に適したものがあるため、事前に確認して止水栓を選定しましょう。
止水栓を自分で交換する手順

それでは、実際に止水栓を交換する際の、一般的な手順を順にご説明します。
水道の元栓を閉める
作業前に必ず建物全体の給水を止めるために、水道元栓を閉め、水が出ない状態にしてください。
給水を止めずに交換作業を行うと、水が噴き出してしまうため注意が必要です。
既存の止水栓を取り外す
モンキーレンチを使用して、止水栓と給水管をつないでいるナットを取り外しましょう。
ナットは反時計回りに回すと緩むため、ゆっくりと取り外します。
その後、止水栓本体も反時計回りに回して取り外してください。
この際、水が少量漏れ出す場合があるため、バケツで受けるようにしましょう。
配管の清掃を行う
古い止水栓を取り外した後は、配管のねじ山や接続部分をきれいに拭き取り、サビや異物を取り除きます。
しっかりきれいにしておくことで、交換した止水栓が固着することを予防できるでしょう。
新しい止水栓にシールテープを巻く
止水栓の先端のねじ部分にシールテープを数回巻きつけ、水漏れ防止の準備をします。
シールテープは先端から数えて2つ目のねじ山から巻き始めてください。
シールテープを巻くときは少し引っ張って張った状態を作り、時計回りに10週前後巻きましょう。
巻き終わった後は、剥がれるのを防止するために指の腹で軽く押さえて、なじませます。
新しい止水栓を取り付ける
止水栓を時計回りにゆっくり締め込んでいき、モンキーレンチで固定します。
このとき強く締めすぎると配管を傷つける恐れがあるため、程よい力で止めてください。。
また、締めすぎたからといって反時計回りに回すことは厳禁です。
反時計まわりに回してしまうとシールテープが剥がれたりもつれたりしてしまうため、シールテープを巻き直すところからやり直す必要があります。
水道の元栓を開けて通水する
止水栓の交換が終わったら水道の元栓を開け、通水して水漏れがないか確認します。
止水栓の周囲をティッシュペーパーなどで軽く押さえてみて、水が染みてこないか確かめましょう。
交換後はしばらくのあいだ使用状況を見て、水漏れや異音などの問題がないか確認することも大切です。
交換作業における注意点

止水栓の交換は比較的シンプルな作業に思えるかもしれませんが、いくつか注意すべき点があります。
まず、配管のねじ山が傷んでいたり、サビが進行したりしている場合には、無理に新しい止水栓を取り付けるのではなく、えひめ水道職人などの水道修理業者に相談することをおすすめします。
無理やり交換することで配管が破損し、配管の交換という大規模な修繕が発生する場合があるでしょう。
また、シールテープの巻き方が不十分だった場合、数日後ににじみ出るような水漏れが発生することもあります。
シールテープはたるませずしっかりと巻いてください。
なお、交換中に止水栓が固くて回らない場合は、力任せに回すと配管が破損する恐れがあります。
モンキーレンチを両手で使って無理に回そうとせず、動かないときはえひめ水道職人などの水道修理業者に依頼した方が安全です。
暮らしの安全を支える止水栓の管理

止水栓は、水まわり設備のトラブル時に私たちの暮らしを守る「見えない安全装置」と言っても過言ではありません。
そんな止水栓の交換はそれほど難しい作業ではないものの、曖昧に行うと安全装置としての役割を果たせなくなるというリスクが発生します。
止水栓の管理は日常生活の安心にも直結する大切な要素です。
私たちえひめ水道職人では、止水栓を含む水まわり設備全般の保守・修理に関して豊富な経験と知識をもとに対応しています。
止水栓の状態や自力での交換に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
大切な住まいを安心して使用し続けるために、止水栓の早めの点検と必要な対応が重要です。