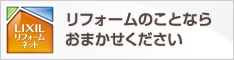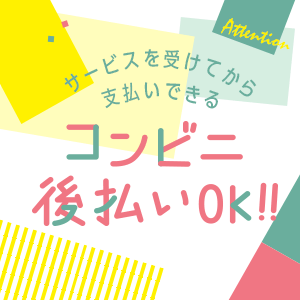水のコラム
トイレタンクの水位は適正?水が止まらない・流れが悪い原因と対処法

トイレの水が流れっぱなしになったり、逆に水の勢いが弱くなったりする症状にお困りではありませんか。これらの問題の多くは、トイレタンク内の水位が適正でないことが原因です。本記事では、トイレタンクの基本的な仕組みから水位トラブルの原因、自分でできる調整方法まで詳しく解説します。
トイレタンクの仕組みと適正な水位とは

トイレが正常に機能するためには、タンク内の水位が適切に保たれている必要があります。水位が高すぎても低すぎても、さまざまなトラブルの原因となります。まずは基本的な仕組みと、適正な水位の見分け方について理解を深めましょう。
タンク内部の水を溜める・流す仕組み
洋式トイレのタンクは、水を効率的に溜めて一気に流す仕組みになっています。レバーを操作すると、レバーに連結された鎖がタンク底部のフロートバルブを引き上げます。これにより、タンク内の水が便器へと勢いよく流れ出る仕組みです。
水が流れ出すと、タンク内の水位が下がり、それに連動して浮き球も下降します。浮き球が下がることでボールタップと呼ばれる給水弁が開き、新しい水の供給が始まるのです。
水位が上昇するとともに浮き球も上昇し、設定された高さに達するとボールタップが閉じて給水が自動的に停止します。この一連の動作により、常に一定量の水がタンク内に確保される仕組みです。
適正水位の見分け方(WLマークの確認方法)
タンクの適正水位は、オーバーフロー管と呼ばれる筒状の部品を基準に判断します。多くのトイレタンクでは、オーバーフロー管の側面に「-WL-」という刻印があり、これが適正水位の目印となります。WLは「Water Level(水位)」の略称です。
刻印がない場合は、オーバーフロー管の先端から2~3センチメートル下の位置が適正水位の目安となります。タンクのフタを開けて水位を確認する際は、この基準に照らし合わせて判断しましょう。
水位が適正範囲から外れている場合は、早めの対処が必要です。放置すると水道代の増加や、トイレつまりなどの二次的なトラブルにつながる恐れがあります。
従来型と節水型トイレの水量の違い
トイレの種類によって、タンクに溜まる水の量は大きく異なります。従来型のトイレでは、適正水位で約13リットルの水が溜まる設計でした。一方、近年普及している節水型トイレでは、4~5リットル程度と大幅に少ない水量で効率的に洗浄できるよう工夫されています。
節水型トイレは少ない水量でも十分な洗浄力を発揮できるよう、便器の形状や水流の設計が最適化されています。そのため、メーカーが定めた適正水位を維持することが特に重要です。
どちらのタイプでも、設計された水量より多すぎたり少なすぎたりすると、本来の性能を発揮できません。特に節水型は水量がシビアに設定されているため、わずかな水位の狂いでも影響が出やすい傾向があります。
水位が適正でないと起こるトラブル

タンク内の水位が基準から外れると、日常生活に支障をきたすさまざまなトラブルが発生します。水位が低い場合と高い場合では、それぞれ異なる症状が現れるため、トラブルの内容から原因を推測することも可能です。早期発見・早期対処のためにも、代表的な症状を把握しておきましょう。
水位が低すぎる場合の症状
タンク内の水位が適正より低い状態では、まず洗浄力の低下が顕著に現れます。流す際の水の勢いが弱くなり、便器内の汚物が完全に流れきらない状況が発生しやすいです。
特に固形物を流す際に問題が起きやすく、トイレットペーパーが便器の奥に残ってしまうことがあります。これが蓄積すると、やがて排水管のつまりにつながりかねません。
また、便器内の水たまり(封水)の量も減少するため、下水からの臭いが上がってきやすくなる場合もあります。衛生面でも好ましくない状態といえるでしょう。
水位が高すぎる場合の症状
水位が高すぎる場合の最も明確な症状は、水が止まらない現象です。本来なら給水が自動的に停止するはずが、いつまでも水が流れ続けてしまいます。
タンク内の水がオーバーフロー管の高さを超えると、余分な水は管を通じて便器へと流れ続けます。この状態では、便器内で常にチョロチョロと水が流れる音が聞こえるはずです。
この症状を放置すると、月々の水道料金が大幅に上昇する可能性があります。1日中水が流れ続けた場合、数十リットルから数百リットルもの水が無駄になることもあり、経済的な損失は決して小さくありません。
水位が低くなる原因と見分け方

水位が適正より低くなる原因はいくつか考えられます。それぞれの原因には特徴的な症状があるため、よく観察することで原因を特定できる場合があります。主な原因を順番に確認し、当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
レバーが元に戻らない
トイレのレバーハンドルが正常に戻らない場合、フロートバルブが完全に閉じず、水が便器側へ流れ続けてしまいます。レバーを操作した後、自然に元の位置に戻るか確認してみましょう。
レバーの動きが渋い、または途中で止まってしまう場合は、軸部分のサビや汚れが原因かもしれません。また、固定ナットの緩みによってレバーの位置がずれていることもあります。
長年使用しているトイレでは、レバー自体の金属疲労や破損も考えられます。レバーを動かした際にガタつきや異音がする場合は、部品の交換時期かもしれません。
フロートバルブの不具合
フロートバルブは、タンク底部で排水口を塞ぐ重要な部品です。この部品が正常に機能しないと、水が常に漏れ出して水位が上がらなくなります。
よくある原因として、フロートバルブとレバーをつなぐ鎖の絡まりがあります。鎖がねじれたり絡まったりしていると、フロートバルブが完全に閉じません。タンクのフタを開けて、鎖の状態を確認してみましょう。
また、鎖の長さが適切でない場合も問題となりやすいです。短すぎるとフロートバルブが浮いた状態になり、長すぎると開く量が不十分になります。適度なたるみがある状態が理想的です。
ゴムフロートの劣化
フロートバルブのゴム部分は消耗品であり、一般的に10年程度で交換が必要です。経年劣化により、ゴムが硬化したり摩耗したりすることで、排水口との密着性が失われます。
劣化の判断方法として、フロートバルブを手で触ってみる方法があります。手に黒い汚れが付着する場合は、ゴムの劣化が進んでいる証拠です。
また、フロートバルブと排水口の間に汚れやカルキが蓄積している場合も、完全に閉じない原因となります。定期的な清掃で予防できますが、劣化が進んでいる場合は部品交換が必要です。
水位が高くなる原因と見分け方

水位が適正より高くなってしまう原因は、主に給水を制御する部品の不具合にあります。これらの部品は複雑な機構になっているため、原因の特定には慎重な観察が必要です。代表的な原因について、詳しく見ていきましょう。
ボールタップの故障
ボールタップは、浮き球の動きに連動して給水を制御する重要な部品です。内部のピストンバルブやパッキンが劣化すると、完全に水を止めることができません。
ボールタップの不具合は、給水音で判断できることがあります。本来なら水位が適正に達した時点で「カチッ」という音とともに給水が止まりますが、故障している場合は微かな水音が続きます。
また、ボールタップ本体から水漏れしている場合もあります。給水管との接続部分や、ボールタップ周辺に水滴が付着していないか確認してみましょう。
浮き球の不具合
浮き球は水位を感知して、ボールタップの開閉を制御する役割を担っています。この部品に問題があると、正確な水位制御ができなくなります。
古いプラスチック製の浮き球では、ひび割れから内部に水が侵入することがあります。水が入った浮き球は重くなって沈んでしまうため、いつまでも「水位が低い」と判断してしまうのです。
浮き球を支えるアームが曲がっている場合も、正しい水位で止まらない原因となります。何かの拍子にアームに力が加わり、本来の角度から変形してしまうことがあるのです。
自分でできる水位調整方法

トイレタンクの水位調整は、基本的な知識と適切な手順を踏めば、自分で行えます。ただし、作業を始める前に必要な準備を整え、安全に配慮しながら進めることが大切です。症状や原因に応じた適切な調整方法を選択しましょう。
作業前の準備と安全確認
水位調整作業を始める前に、まず止水栓を閉めることが重要です。止水栓は通常、トイレの給水管に設置されており、マイナスドライバーで時計回りに回すと閉まります。
次に、タンクのフタを慎重に取り外します。陶器製のフタは重く割れやすいため、両手でしっかりと持ち、安定した場所に置きましょう。手洗い管付きのタンクでは、ホースを外す必要がある場合もあります。
作業に必要な工具も事前に準備しておきましょう。マイナスドライバー、モンキーレンチ、ゴム手袋などがあると便利です。また、水が飛び散る可能性があるため、タオルも用意しておくと安心です。
浮き球タイプの調整方法
浮き球が付いているタイプのボールタップでは、浮き球を支えるアームを曲げることで水位を調整します。この作業は比較的簡単ですが、力加減が重要です。
水位を上げたい場合は、アームの中央部分を上向きに緩やかに曲げてください。反対に水位を下げたい場合は、下向きに曲げます。一度に大きく曲げると破損の恐れがあるため、少しずつ調整しましょう。
調整後は止水栓を開けて水を溜め、適正水位になっているか確認します。必要に応じて再調整を行い、最適な位置を見つけてください。アームの付け根にあるナットが緩んでいる場合は、しっかりと締め直すことも忘れずに行いましょう。
調節ネジタイプの調整方法
最近のトイレでは、調節ネジや調節リングで水位を調整できるタイプが主流です。このタイプは、ドライバー1本で簡単に調整できるメリットがあります。
調節ネジは通常、ボールタップ本体の側面や上部に設置されています。水位を上げる場合は時計回りに、下げる場合は反時計回りに回します。調節リングタイプでは、90度回転させると約8ミリメートル水位が変化する製品が多いようです。
メーカーによって仕様が異なる場合があるため、可能であれば取扱説明書を確認してから作業を行いましょう。調整は少しずつ行い、その都度水位を確認しながら最適な位置を見つけてください。
部品交換が必要な場合の対処法
水位調整を行っても改善しない場合や、明らかに部品が劣化している場合は、新しい部品への交換が必要です。主な交換部品と、その交換方法について説明します。
フロートバルブの交換は比較的簡単な作業です。まず鎖を外してから古いフロートバルブを取り外し、新しいものを取り付けます。鎖の長さは、フロートバルブが完全に閉じた状態で少し余裕がある程度に調整しましょう。
ボールタップの交換はやや複雑ですが、手順を守れば自分でも可能です。給水管との接続を外し、タンクに固定されているナットを緩めて古いボールタップを取り外します。新しいボールタップを取り付ける際は、パッキンの向きに注意し、各部のナットをしっかりと締めてください。
部品交換後は必ず水漏れがないか確認し、数回水を流して動作に問題がないかテストしましょう。不安な場合は、無理をせず専門業者に相談することをおすすめします。
トイレ修理部品が購入できる愛媛県内のホームセンター
トイレの修理部品は、お近くのホームセンターで購入できます。愛媛県内には品揃えが豊富な大型店舗が複数あり、専門スタッフのアドバイスも受けられます。
DCM 美沢店
住所:愛媛県松山市美沢1丁目9番33号
営業時間:8:00〜20:00
松山市内でも特に品揃えが豊富な大型店舗です。DIY用品から園芸用品まで幅広く取り扱っており、トイレ修理部品も各種メーカーの製品を揃えています。 スタッフの商品知識も豊富で、部品選びに迷った際は適切なアドバイスを受けられます。
コーナン 三津浜店
住所:愛媛県松山市大可賀3丁目670-11
営業時間:8:00〜20:00
プロ向けの「コーナンPRO」も併設されており、一般的な修理部品から専門的な工具まで幅広く取り扱っています。 価格も比較的リーズナブルで、まとめ買いにも便利な店舗です。
DCM 新居浜店
住所:愛媛県新居浜市瀬戸町甲4101
営業時間:8:00〜20:00
新居浜市の老舗ホームセンターで、地域密着型のサービスが特徴です。トイレ修理に関する相談にも親身に対応してくれます。 売り場も見やすく整理されており、初心者でも目的の商品を見つけやすい店舗です。
トイレのトラブルは「えひめ水道職人」へ
トイレタンクの水位調整は、原因を正しく把握すれば自分で対処できる場合も多くあります。しかし、作業に不安がある場合や、調整しても改善しない場合は、迷わずプロの力を借りましょう。
えひめ水道職人は、愛媛県広域で水回りのトラブルに対応している水道局指定工事店です。24時間365日受付対応しており、年末年始やお盆期間中でも変わらずサービスを提供しています。お電話をいただければ、最短30分から1時間ほどで現地へ駆けつけ、経験豊富な専門技術者が的確な診断と修理を行います。
料金についても、作業前に詳細な見積もりを提示し、お客様が納得された上で作業を開始するため安心です。お支払い方法も現金はもちろん、各種クレジットカード、銀行振込、QRコード決済、コンビニ支払いなど多様な方法からお選びいただけます。
トイレの水位トラブルでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。